

キャリアアップを目指す!
詳しくはこちら
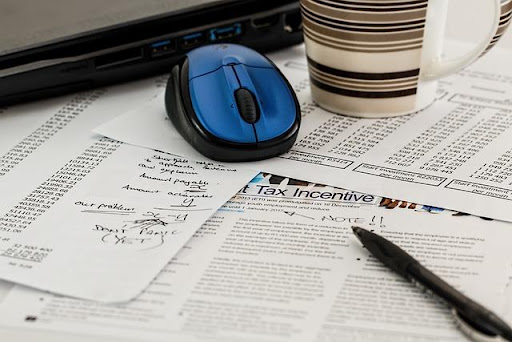
税効果会計とは、企業における会計処理の税金と実際に掛かった税金の差を調整することで、税務上の益金(損金)と会計上の収益(費用)に相違がある場合に正しい法人税に修正するものです。
税効果会計を行う理由は、当期純利益を算出する際に「企業会計における利益の計算方法」と「税務会計における計算方法」が異なるため、差異が生まれてしまうからです。
(企業会計と税務会計についても後ほど説明いたします。)
企業が営利目的で事業を行う際に、経済活動に関わる収入や支出を記録し報告することを「企業会計」と呼びます。
企業会計は主に財務会計、税務会計、管理会計の3つに分かれます。
この差異を調節し、決算書を作成する際に正しく業績を反映することが税効果会計の一番の目的です。税効果会計は当期純利益を算出する上で非常に重要な役割があります。
税効果会計が適用される企業は、主に以下の3つです。
他の企業は任意で税効果会計を導入するか選択できます。
税効果会計は主に上場企業に適用され、他の企業は任意になります。
前述しましたが、税効果会計を行うことによって当期純利益を算出する際に生じる差異を調整し、正しい決算書を作成できます。
そのため、税効果会計をしなければ投資家や金融機関に正しい財務状況をお伝えできないからです。
なぜ、このような差異が起きるのでしょうか。それは企業会計と財務会計の違いにあります。
そもそも企業会計と税務会計では会計の目的が異なります。
となっています。
企業会計は株主などに報告するための財務会計と、企業の中で意思決定を行うための財務会計に分かれます。
営利企業が財務状況を報告するために行う会計であり、収益から費用を引いて利益を算出します。目的も会社の実績などを正確に表すことになっています。
税務会計では、会社の成果をもとに国や地方公共団体に報告することを目的に法人税法などのルール下で行われます。
ですので、「税収の確保」や「税の公平性」という観点が加わり修正を加えたものが税務会計となり、益金から損金を引いて所得を算出します。
企業会計における「収益」は税務会計における「益金」と一緒のようなものですが「税収の確保」や「税の公平性」という観点から調整が入るため「収益=益金」ではありません。
このように税務会計における観点の違いから差異が生まれます。
税効果会計の方法は2種類あり、「資産負債法」と「繰延法」に分かれます。
大まかに分けると、資産負債法は貸借対照表(B/S)繰延方では、損益計算書(P/L)を重視しています。
資産負債法は、企業会計基準適用指針 第28号 89項1号にて規定されています。
簡単に説明すると、資産負債法では会計上の資産と税務上の資産の違いと差異が解消される時に重きを置きます。
資産負債法とは、会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額との間に差異が生じており、当該差異が解消する時にその期の課税所得を減額又は増額する効果を有する場合に、当該差異(一時差異)が生じた年度にそれに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する方法である。
(企業会計基準適用指針 第28号 89項1号より引用)
繰延法は、企業会計基準適用指針 第28号 89項2号にて規定されています。
資産負債法と異なる点は、利益の違いに重きを置きます。
繰延法とは、会計上の収益又は費用の額と税務上の益金又は損金の額との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくもの(期間差異)について、当該差異が生じた年度に当該差異による税金の納付額又は軽減額を当該差異が解消する年度まで、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法である。
(企業会計基準適用指針 第28号 89項2号より引用)
税効果会計では「対象になる税金」と「対象にならない税金」が分けられています。税効果会計の対象になる税金を以下に記載します。
・ 法人税
・ 住民税(均等割額を除く)
・ 利益を課税標準とする事業税(所得割)または地方法人特別税
税効果会計の対象となる税金は、収益に関わる金額を課税の対象とする税金です。
そのため、以下に記載する税金は税効果会計の対象となりません。
・ 収入を課税基準とする事業税
・ 住民税均等割額
・ 資本割や付加価値割などの外形標準課税の事業税
・ 事業所税
・ 固定資産税
・ 過少申告加算税や重加算税などの罰科金
以上をふまえて、税効果会計の「対象になる税金」と「対象にならない税金」をしっかりと理解しましょう。
実際に税効果会計をする際の基本的な手順を以下に記載します。
1. 差異を明確にする
2. 差異を回収できる可能性を検討する
3. 法定実効税率を計算する
4. 計算した法定実効税率を使用し繰延税金資産(負債)を算出する
5. 税効果会計の仕訳をして処理する
詳しく解説していきます。
1. 差異を明確にする
まず会計上の税引前当期純利益と税法上の課税所得から差異を計算します。算出した永久差異と一時差異のうち税効果会計では一時差異のみが適用となるので、一時差異だけを集計します。
差異がある状態では税引前当期純利益に対して法人税等の金額が釣り合わなくなってしまうため、「法人税等調整額」という勘定科目を用いて調整するのが一般的です。
2. 差異が回収できる可能性を検討する
1.で算出した一時差異を回収できる可能性の程度を検討します。十分な課税所得が差異の解消される予定の年度に見込まれるかどうか、具体的には以下の判断項目に基づいて確認します。
・ 収益力があるか
・ 差異が解消される見込年度の将来加算一時差異
・ 課税所得が生じるかどうかのタックスプランニング
回収の可能性が高ければ、将来見込まれる税金を減らすことができます。回収不能となり損失を計上するリスクも減らせるため、しっかりと検討しましょう。
3. 法定実効税率を計算する
法定実効税率とは、法人税や事業税・住民税などの表面税率を使い算出される税率のことです。表面税率とは法律が定めている税率のことを指し、税金の納付や申告の際に使われます。税効果会計の場合は表面税率ではなく法定実効税率を使用します。
法定実効税率を計算する場合は、以下の計算式を用いて算出します。
法定実効税率=(法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率)
4. 計算した法定実効税率を使用し繰延税金資産(負債)を算出する
一時差異を解消するために繰延税金資産(負債)という勘定科目を使い、法人税等の金額を調整していきます。
繰延税金資産は将来の税金の支払いを減らす効果のある資産で、税金を前払いしている場合に計上する勘定科目です。
一方の繰延税金負債とは、会計上の収益と税法上の益金を一致させるために計上する勘定科目です。
一時差異の中から繰延税金資産(負債)の金額を算出し、3.で算出した法定実効税率を乗じて金額を確定します。
5. 税効果会計の仕訳をして処理する
最後に税効果会計の仕訳をしていきます。具体的な仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 |
| 繰延税金資産 xxx,xxx | 法人税等調整額 xxx,xxx |
「法人税等調整額」とは損益計算書の勘定科目の1つです。一時差異を解消するために使用します。繰延税金資産という将来の税金の支払を減らす効果のある資産を得た、つまり収益を得たとして計上されます。
借方に繰延税金資産と金額を計上し、貸方に法人税等調整額と繰延税金資産と同じ金額を計上します。
| 借方 | 貸方 |
| 法人税等調整額 xxx,xxx | 繰延税金資産 xxx,xxx |
一時差異が解消された場合は資産を失った、つまり損失が発生したとなるため法人税等調整額が費用となり上記と反対の仕訳をします。
繰延税金資産は将来の税金の支払いを減らす効果があるため、貸借対照表の資産に計上されます。
他社の決算書で繰延税金資産が計上されている場面はよく見る機会があると思いますが、一方の繰延税金負債が計上されている場面は限定的です。
繰延税金負債を計上するのは「会計上の利益を税務上の益金に合わせる場合」ですが、実務で使う場面は限られています。繰延税金負債を計上するのは「固定資産の圧縮記帳に記載する圧縮積立金」や「投資有価証券の評価益を計上する」場合です。
将来の税金を多く支払う義務である繰延税金負債は貸借対照表の負債(貸方)に計上されるため、一時差異が解消された場合は繰延税金負債を借方に計上して仕訳をします。
繰延税金資産が計上されるのは、将来の税金の支払が安くなる場合のみです。つまり、税金を納められるくらい利益が出ている会社でしか計上ができない勘定科目になります。
もし繰延税金資産を計上した後、経営悪化等により支払えなくなった場合は、支払えないと分かった時点で繰延税金資産を取り消さなければなりません。取り消すとは、損失が出ることと同義になります。回収の可能性を慎重に検討し、堅実に税効果会計の処理をしていきましょう。

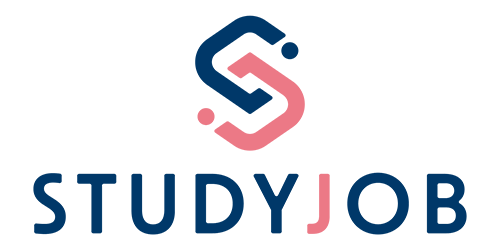
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
SEARCH